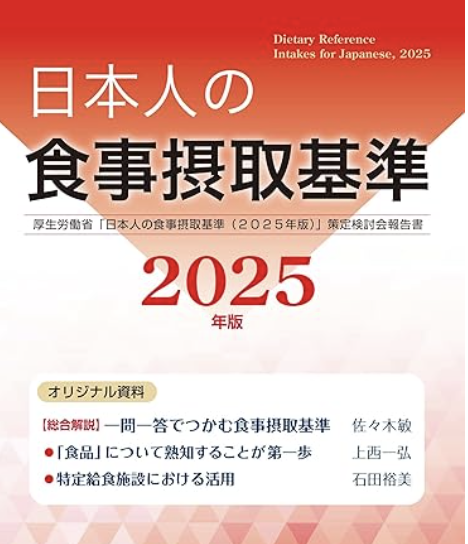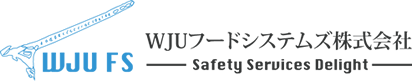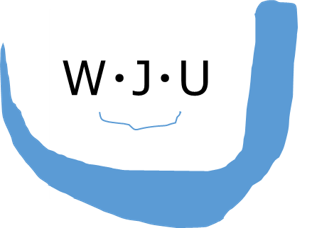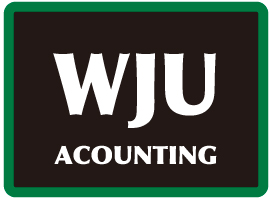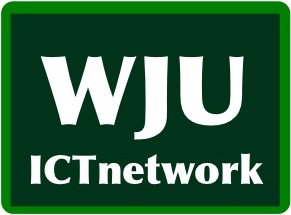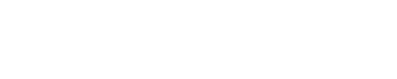健康的な食生活の指針となる「日本人の食事摂取基準」が2025年版(令和7~12年度適用)として改定されました。5年ごとに最新の科学的知見を反映して更新されるこの基準は、国民の健康維持・増進に重要な役割を果たしています。今回は、2020年版からの主な変更点とその適切な活用方法について解説します。
2025年版の主な改定ポイント
栄養素に関する変更点
1. 食物繊維 食品成分表の改訂による測定法の変更に伴い、目標量が見直されました。成人の多くで目標量が増加傾向にあります。これは私たちの健康維持において食物繊維の重要性が再認識された結果といえるでしょう。
2. 鉄 最新の科学的知見から、鉄の過剰摂取リスクは限定的であるとの結論に至り、成人における耐容上限量が削除されました。このことは、特に鉄欠乏性貧血リスクの高い女性にとって朗報といえます。
3. ビタミンD ビタミンDの目安量が増加しました。骨の健康だけでなく、免疫機能などにも関わるビタミンDの重要性がより強調される形となっています。
4. アルコール 従来の扱いから変更され、栄養素ではなく「エネルギー産生栄養素バランス」の項目でエネルギー源となる物質として位置づけられることになりました。
疾病予防に関する変更点
1. 骨粗鬆症 生活習慣病等と関連する疾患として新たに追加され、骨の健康維持の重要性が明確に示されました。高齢化社会における重要課題として認識されています。
2. 継続される重点事項
- 生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病)の発症予防・重症化予防
- 高齢者の低栄養予防・フレイル予防(特にたんぱく質摂取の重要性)
食事摂取基準の適切な活用方法
1. PDCAサイクルに基づく運用
効果的な栄養管理のためには、以下のPDCAサイクルが重要です:
- Plan(計画): 食事摂取基準に基づいた栄養管理目標の設定
- Do(実施): 設定した計画に沿った食事提供や栄養指導の実施
- Check(評価): 摂取状況や健康状態の定期的な評価
- Act(改善): 評価結果を踏まえた栄養管理計画の見直し
2. 個別化対応の重視
単に基準値を満たすだけではなく、対象者の年齢、性別、身体活動レベル、健康状態などに応じた個別化対応が必要です。一般集団と特定集団(疾病リスクの高い人々など)での適切な使い分けも重要なポイントです。
3. 包括的アプローチの実践
全ての国民が健やかな生活を送れるよう、基準を「Inclusion(包括性)」と「Implementation(実施)」の二側面から活用することが推奨されています。誰一人取り残さない栄養政策の実現を目指しています。
4. 予防と重症化防止の両輪
食事摂取基準は、健康な人々の生活習慣病予防と、すでにリスクを抱える人々の重症化予防の両面から活用することが大切です。特に後者においては、医療専門家との連携が不可欠となります。
5. エビデンスに基づく栄養指導(EBN)
科学的エビデンスに基づく栄養指導(Evidence-Based Nutrition)の実践が推奨されています。最新の研究知見を踏まえた栄養障害のリスク評価と予防に活用しましょう。
6. 専門家による解釈と応用
管理栄養士・栄養士が専門知識をもとに基準を適切に解釈し、個人や集団の栄養評価および食事指導の場で応用することが求められています。
7. 定期的なモニタリングと評価
栄養状態や健康状態を定期的にモニタリングし、必要に応じて栄養管理計画を調整することで、より効果的な健康管理が可能になります。
8. 多職種連携の推進
医療機関では医師や他の医療スタッフとの連携、地域・行政では健康増進施策への活用など、多職種・多分野での連携が重要です。
まとめ
「日本人の食事摂取基準2025」は、単なる数値の集合ではなく、国民の健康を支える重要な指針です。ここで強調されているのは、基準値を絶対的な規範として硬直的に捉えるのではなく、科学的根拠に基づきながら個々の状況に応じて柔軟に適用することの重要性です。
私たち一人ひとりの健康維持・増進のために、この基準を正しく理解し、日々の食生活に取り入れていくことが大切です。特に今回の改定で注目された食物繊維やビタミンD、そして高齢者の健康維持に関する知見は、超高齢社会を迎えた日本において、より健やかな生活を送るための重要な手がかりといえるでしょう。
ただ医療・福祉給食においてはヒト・モノの資源がなくなってきています。実現するためには抜本的な見直しが必要ではないでしょうか?
投稿者:米須靖朗